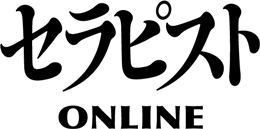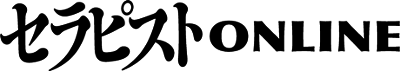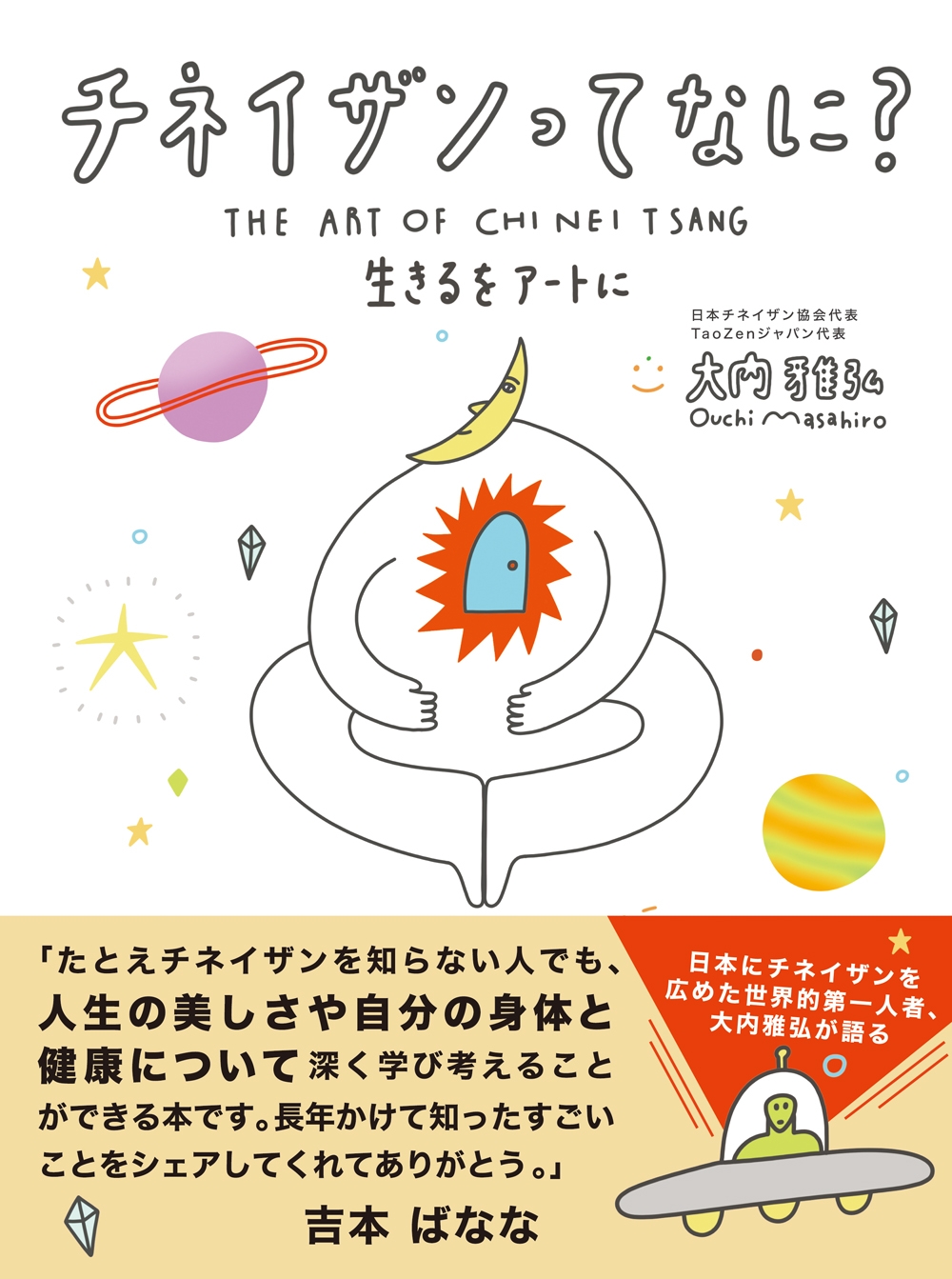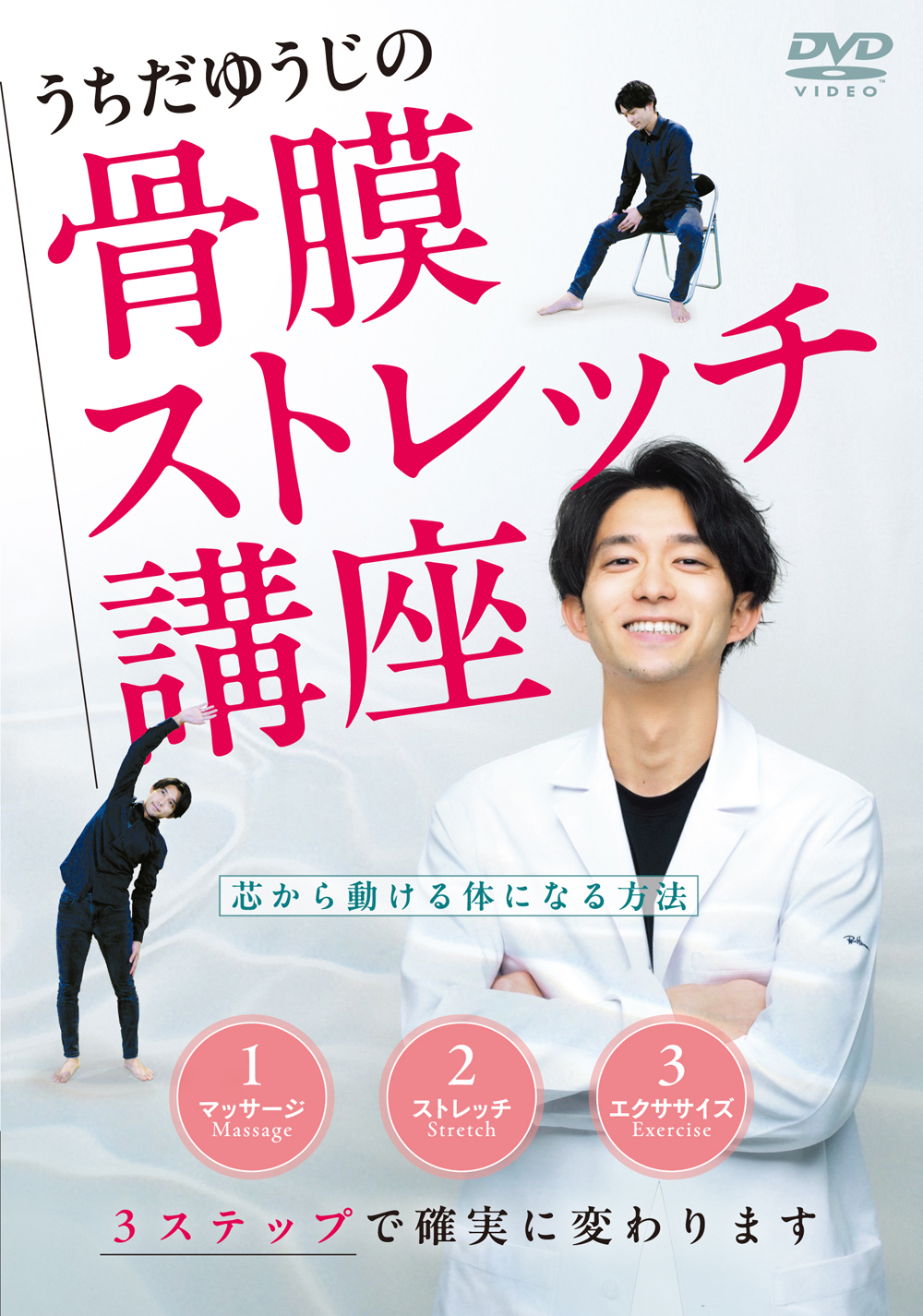セラピストがクライアントと接する際に最も重要なことは、「聴くこと」です。しかし、「聴く」と一口に言っても、クライアントのタイプは千差万別。マニュアル通りに進められるものではありません。現在発売中のセラピスト10月号の「聴き方、話し方特集」にて、聴くときの心構えなどを掲載しています。ここでは聴き方のページで登場していただいた椎原澄さんに、誌面では紹介できなかったセッションで注意すべき点を解説します。
構成◎本誌編集部
1. 人間の感情は「共感」と「反感」で構成されている

まず、コミュニケーションの前提となる人間の感情について考えてみましょう。人間の感情にはさまざまなものがありますが、究極的には人の感情は「共感/快」と「反感/不快」の2つに分けられます。私を分かってくれるから嬉しい(=共感)、分かってくれないから悲しい(=反感)といった具合です。複雑な感情とは、この2つにさまざまな条件や体験などが加味されたものです。
たとえば、仕事は楽しい(=共感)が、上司の皮肉や管理的態度に耐えられない(=反感)のように、共感と反感のバランスがうまくとれない状況に陥ると、ストレスが増幅され、心身の調子を崩すことがあります。
2. セラピストに必要な「共感」
セラピストには「共感」が必要だと言われますが、共感とはどういうことでしょうか。実はクライアントに対して、共感と同調を混同しているセラピストは多くいます。共感とは、相手の考えを思考と感情で理解することですが、同調とは無意識に、感情的にのめり込んでしまうことを言います。
セラピストはクライアントに一旦共感はしても、同調してはいけないのです。なぜなら、多くのクライアントには、「私はわかってもらえていない」という心理が働いています。これに同調してしまうと、その心理のみを増幅し、マイナス思考のリフレインが起きやすいのです。結果、クライアントの話を長時間聴き続けることになり、セラピスト自身が疲弊してしまいます。
クライアントは、一旦感情を込めて「わかってもらえた」という安心感を持てば、そこから切り替える力が生まれます。セラピストはそこからプラス思考に向かう質問をすればよいのです。
3. 何を質問するか考えてはいけない
では、どのような質問をすれば良いのでしょうか。セラピスト向けの講座で「傾聴よりも質問に注力して下さい」と言うと、「何を質問すれば良いだろう」と考え始めてしまう人がいます。その途端にセラピストは、傾聴を忘れて相手の言葉を聞いていません。
傾聴の際の質問のコツは、クライアントの言葉から質問のタネを探すことです。たとえば、紙面でも紹介した「〜のに」「〜けど」「〜れば」といった言葉は、重要なポイントで「のに?」「何が『けど』なのでしょう?」とセラピストが言うだけで質問になり、クライアントが自身の感情について振り返るきっかけとなります。
4. ケーススタディ
 「会社でのコミュニケーションが上手くいかない」という悩みを抱えていたクライアントのケースをご紹介します。
「会社でのコミュニケーションが上手くいかない」という悩みを抱えていたクライアントのケースをご紹介します。
このクライアントは、「周りの人たちは、君は変わらなくてはダメだと言います。でも僕は自分を変えたくありません」とセッションで訴えてきました。
さていったい、このクライアントは「何を変えたくない」のでしょうか?
よくあることですが、周囲からそう言われると本人は「人格全てを否定された」と受け取ってしまいます。
セラピストができる質問は「あなたのどこが変わればいいのかしら?」とか「どんな習慣を変えればいいと思う?」です。
自分の本質を変える必要はない。どこかで身につけてしまったマイナス面を変えればいいだけ、ということに気づいてもらう質問です。
このように、あくまでも、クライアントがふと考えてみたくなるような質問をすることで、クライアントに「安心感」を与え、「共感」と「反感」にこびりついているマイナスの感情を見直すよう、働きかけてみて下さい。
著者プロフィール

椎原澄(しいはらすみ)さん
コーチ、セルフトークコンサルタント。出版社やデザイン会社を経て、コーチングやビジネスプロデューサーとして、数々の企業や学校の研修を実施。現在はセラピスト養成会社「ジェイ・コミュニケーション・アカデミー」講師、一般財団法人snug代表理事などを兼務。著書に『悩みの9割は「言い換え」で消せる』(小社刊)がある。
取材協力◎株式会社ジェイ・コミュニケーション・アカデミー
TEL03-3373-2378 http://www.j-c-a.co.jp/